🗞️〖雑学コーナー⑥〗外壁トリビア・社寺仏閣編📰
2025年04月24日 16:51:00
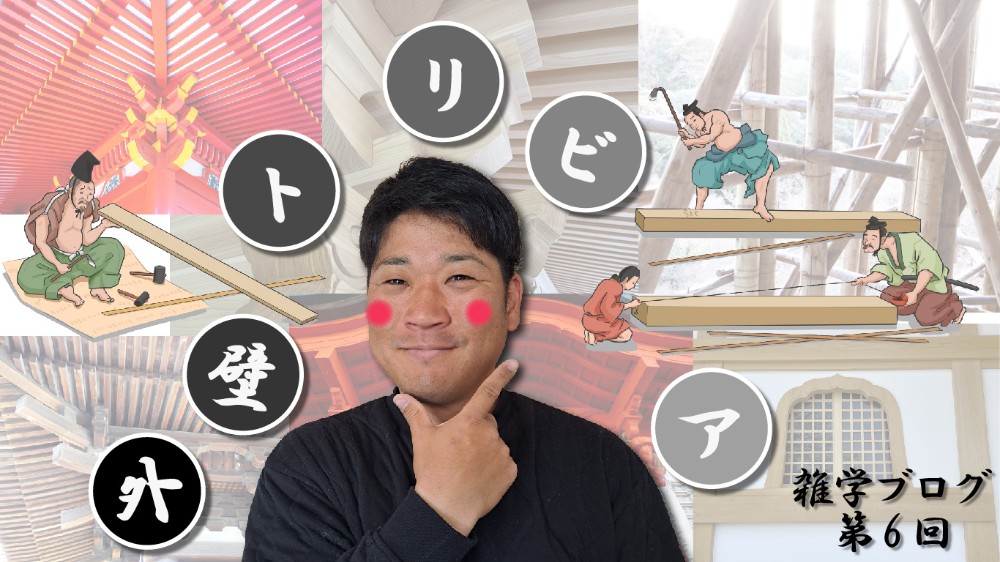
今回のブログは〖雑学コーナー〗第6回目!
神社仏閣の外壁にまつわるトリビアをご紹介していこうと思います⛩️🏯
では早速!!
1. 木材が主役🌲
社寺仏閣は木造建築が基本。
特に使用されるのは日本の気候に適した「檜(ひのき)」「欅(けやき)」「杉(すぎ)」など。
檜は防虫性・耐久性・香りに優れており、伊勢神宮などでも用いられています。
建物全体が「生きた素材」でできており、年月とともに変化していく姿も魅力です。
2. 塗装しない美学🎨
神社では、あえて木材を無塗装のまま使う「白木造(しらきづくり)」が伝統。
これは、清らかさ・潔白さを表現しています。
風雨や紫外線で徐々に飴色や灰色に変化していくのもまた「自然との一体」を大切にする日本の価値観が現れています。
3. 漆塗りの防水効果💧
仏閣(お寺)では、外壁や柱に漆(うるし)が施されることがあります。
これは単に美しさを演出するだけでなく、防水性、防腐性、抗菌性に優れ、木材を長持ちさせる役割を持ちます。
特に黒漆や赤漆は、高級感と厳粛さを演出します。
4. 朱塗りの意味❤️
神社でよく見る「朱色」の外壁。
この色には魔除け、疫病退散の意味が込められています。
朱色の顔料は昔、「丹(に)」と呼ばれ、水銀を含む鉱物を使用していました(現在は代替品)。
神聖な色として、神様を祀る建物にふさわしいとされます。
5. 鏡板の装飾🪞
神楽殿や能舞台などの背景に見られる「鏡板」は、しばしば松の絵などが描かれます。
外壁にもこのような絵画や神聖な図像が施されることがあります。
これは神の依代(よりしろ)を意味し、建物に神聖な空気を与えます。
6. 風雨に耐える庇(ひさし)🌧️
外壁の上には深い庇(ひさし)があり、これは強い日差しや雨風から壁面や柱を守ります。
庇の角度や長さは、建物の構造美を作る大切な要素でもあります。
日本の多湿な気候に合わせた工夫です。
7. 長押(なげし)のデザイン🪵
「長押(なげし)」とは、柱と柱を水平につなぐ化粧材。
外壁では、この部材が意匠的に使われることがあり、建物のリズム感や格調を生み出します。
現代建築でも意匠に応用されることがあります。
8. 千木・鰹木との一体感🔱
屋根の上にある「千木(ちぎ)」や「鰹木(かつおぎ)」は神社のシンボルですが、それらと外壁全体の色彩・意匠が調和するように設計されています。
外壁の色や形状は、これら上部装飾との統一感を重視して作られているのです。
9. 土壁と漆喰の技術🧱
一部の仏閣では木の外壁に「土壁」や「漆喰(しっくい)」が使われています。
漆喰は石灰を主成分とし、調湿・防火に優れています。
豪雪地帯や火災対策を重視した地域に多く見られ、伝統的左官技術の粋が詰まっています。
10. 狛犬と一緒に🐕🦺
神社の入り口には「狛犬(こまいぬ)」が外壁近くに鎮座します。
彼らは建物の守り神であり、阿吽の呼吸を象徴します。
建物の外構としての美しさと同時に、精神的な結界の役割も担っています。
11. 極彩色の彫刻🐉
日光東照宮のような仏閣では、外壁に「見ざる・言わざる・聞かざる」や龍、鳳凰などの極彩色の彫刻がびっしり。
これらは仏教の教えや神仏習合の象徴を芸術的に表現したもので、装飾美と信仰が融合しています。
12. 「雨落ち」の工夫💦
外壁の下には「雨落ち」や「犬走り(いぬばしり)」と呼ばれる石や砂利のゾーンがあります。
これは、雨水の跳ね返りを防ぎ、外壁が傷むのを防止する日本独自の知恵です。
13. 木組みの技術🔩
社寺の多くは「釘を使わずに組む」木組み(ほぞ・仕口)技術で作られています。
外壁部分にもこの構造が活かされており、地震にも強いです。
数百年保つ理由はこの技術にあります。
14. 破風板の意匠🌀
屋根の端に取り付けられる「破風板(はふいた)」は、外壁との接合部分にあります。
これには風雨の侵入を防ぐ機能と、家紋や彫刻を施して美観を高める装飾的な意味もあります。
15. 板張りのパターン📏
外壁に使う木板の張り方には様々な種類があり、「縦板張り」「横板張り」「なぐり仕上げ」などが存在します。
それぞれ地域性や建築様式により異なり、建物を見ることでその土地の歴史もわかります。
16. 社寺の「垣根」も外壁の一部⛩️
社や仏堂を囲む「垣根」「玉垣(たまがき)」は、外壁と同様に神聖な空間を囲う役割を果たします。
これにより「聖域」と「俗世」がはっきりと分けられる構造になっています。
17. 年中行事に合わせた飾り🎎
正月や例祭の時期になると、外壁には「しめ縄」「紙垂(しで)」などが飾られます。
これは神を迎える準備であり、建物が一時的に儀式空間に変わることを示します。
18. 風通しのための格子🌬️
仏閣の外壁には「格子窓(こうしまど)」が設けられることがあり、これは通風・採光を目的としています。
同時に、外から内部が見えにくくなるため、精神的な境界線としても機能しています。
19. 色の意味と流派の違い🌈
浄土宗、真言宗、天台宗など宗派によって、外壁の色や装飾に宗教的シンボルや哲学が反映されています。
例えば、浄土宗では極楽浄土を意識した金色や青色の装飾が見られることがあります。
20. 再建でも伝統技法🛠️
火災や地震で倒壊してしまった社寺でも、再建時には伝統的な材料・工法を用いて外壁も忠実に復元します。
たとえば金閣寺や法隆寺などは何度も再建されていますが、そのたびに歴史を継承しています。
📸 こういった外壁の「細部」を観察することで、建物の意味や歴史、地域性がグッと見えてきますよ!
御朱印巡りもいいですが、外壁ひとつとっても、そういった宮大工の職人さんの粋な仕事や、ひとつひとつがその宗教観による意味のある構造をしていると考えるだけで、また違った趣の印象に感じるのではないでしょうか❓





